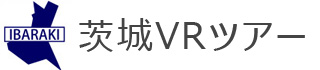大子町の観光おすすめ神社・御朱印拝受案内
- 大子町神社一覧
- 神社VRツアーマップ
- 大子町の観光
- 大子町のお寺
大子町の神社おすすめスポット10件
八溝嶺神社(観光・登山名所)
 延喜式内社、八溝山山頂、梵天祭(大子町無形民俗文化財)
延喜式内社、八溝山山頂、梵天祭(大子町無形民俗文化財)近津神社(下野宮・名所)
 近津三社、中田植(大子町指定文化財)、鉾杉(茨城県指定文化財)、延喜式内社
近津三社、中田植(大子町指定文化財)、鉾杉(茨城県指定文化財)、延喜式内社近津神社(町付)
 近津三社、徳川頼房公奉納の石鳥居(大子町有形文化財)
近津三社、徳川頼房公奉納の石鳥居(大子町有形文化財)近津神社(上野宮)
 近津三社、下野宮の近津神社から分祀
近津三社、下野宮の近津神社から分祀十二所神社
 十二所神社春季例大祭(大子町指定文化財)、茨城百景「大子の史跡」
十二所神社春季例大祭(大子町指定文化財)、茨城百景「大子の史跡」十二所神社 蒟蒻神社
 蒟蒻業界の始祖・中島藤右衛門を祀る神社
蒟蒻業界の始祖・中島藤右衛門を祀る神社諏訪神社(小生瀬)
 神馬の像、随神門、弓祓い神事(近的の儀)
神馬の像、随神門、弓祓い神事(近的の儀)男体山神社
 大子町頃藤、登山口、白滝、奥の院
大子町頃藤、登山口、白滝、奥の院関戸神社
 別名・関戸米神社、焼山関、大子町文化遺産、御朱印
別名・関戸米神社、焼山関、大子町文化遺産、御朱印越方神社
 越方大明神、赤い太鼓橋・鳥居、髄神門、橋くぐり祈願
越方大明神、赤い太鼓橋・鳥居、髄神門、橋くぐり祈願
大子町の神社VRツアーマップ
八溝嶺神社:大子町の名所
八溝嶺神社は、茨城県の最高峰の八溝山に鎮座する神社で、平安時代には陸奥国の延喜式内社でした。戦国時代に佐竹氏が、陸奥国に進出し現在の大子地域が常陸国になった経緯で、現在は、茨城県にある陸奥国の延喜式内社です。創建は景行天皇40年(110年)、日本武尊東征にて八溝の賊を打ち払い大己貴命・事代主命を祀ったのが始まりとされています。
※参考:大己貴命(おおあなむちのみこと)は、日本神話における国造神の一人で、一般的には大国主命(おおくにぬしのみこと)として知られています。 事代主神(ことしろぬしのかみ)は、日本神話に登場する神で、大国主神の子で、海や漁業、商業、託宣の神として信仰されています。 また、恵比寿神(えびす)が事代主神と同一視されることも多く、商売繁盛や大漁の神として知られています。
八溝嶺神社で行われる若衆30人程で梵天(ぼんでん)を担いで山頂へ登る梵天祭は、大子町の無形民俗文化財に指定されています。御朱印は、年に1度の5月3日に行られる梵天祭の時に拝受できます。
麓に八溝山の一の鳥居があります。
- 所在地〒319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮字八溝2119
- 参考大子町 八溝嶺神社の梵天祭 紹介ページ
八溝山神社の地図
近津神社(下野宮):大子町の名所
※本サイトでは、地域スポット案内は北側から説明していますが近津神社は説明の都合で下、中、上の順で説明しています。下野宮、町付(中の宮)、上野宮の近津神社は、ともにかつて保内42ヶ村の総社として「近津三所大明神」と尊称されていました。
下野宮の近津神社は、延喜式内社の稲村神社(社格小)の論社で大子町のおすすめ観光スポットです。
【御祭神】級長津彦命 (しなつひこのみこと)、面足命 (おもだるのみこと)、惶根命 (かしこねのみこと)
※級長津彦命は、日本神話に登場する神で、日本書紀では級長津彦命と表記され、神社の祭神としては志那都彦神などとも書かれる。
面足命と惶根命は、日本書紀では兄を面足尊、妹を綾惶根尊(あやかしきね)と表記され、神世七代の第六代目の神として、人体の完成や、陰陽の調和などを象徴するとされます。
下野宮の近津神社は、大子町の近津神社3社の中心の神社です。中田植と呼ばれる江戸時代以前から続いている祭事があり、大子町指定文化財となっています。社殿の左にある杉の巨木は、奥州征伐に向かう源義家が鉾を立てかけたという言い伝えにより鉾杉と呼ばれ、茨城県指定文化財で大子町のパワースポットです。
御朱印は、元旦と御田植祭り(毎年夏至の日)の時に拝受できます。
- 所在地〒319-3555 茨城県久慈郡大子町下野宮1626
- 連絡先:近津神社・電話:0295-72-8329
- 参考大子町 近津神社の中田植 紹介ページ
近津神社(下野宮)の地図
近津神社(町付):大子町町付
慶運4年(西暦707年)の勧請で、下野宮、上野宮と共に近津三所大明神と尊称されています。近津三所大明神の祭神は、級長津彦命、面足命、惶根命で同じです。また、上野宮・下野宮・中ノ宮(町付)の近津神社に大晦日の夜から元日の朝にかけて巡拝する「三社参り」という風習があります。
大子町の町付の近津神社にある石鳥居は、寛永11年(1634年)に水戸藩初代藩主の徳川頼房公が奉納したもので、大子町の有形文化財(建造物)となっています。
- 所在地〒319-3702 茨城県久慈郡大子町町付1218
- 参考大子町 近津神社(中宮)の石鳥居 紹介ページ
近津神社(町付)の地図表示
近津神社(上野宮):大子町上野宮
大子町には近津神社が下野宮、町付(中の宮)、上野宮の3社あり、近津三社大明神と言われ大子町のおすすめスポットです。上野宮の近津神社は、下野宮の近津神社から分祀された神社です。一の鳥居、随神門、広い境内に拝殿・本殿がある立派な神社です。一の鳥居から拝殿までの参道の距離は、約110メートルです。
- 所在地〒319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮3208
- 連絡先:近津神社・電話:0295-72-8329
近津神社(上野宮)の地図
十二所神社:大子町の名所
十二所神社は、社伝では、当地方の開発の守護神として神亀4年(西暦727年)に創建されました。神亀4年は、蝦夷の反乱が起きた年、多賀城が設置された年です。また、慶長(西暦1596年)の始め佐竹義宣の寄進で社殿が改築され、明治43年(西暦1910年)4月、本町の大火に類焼し、社殿・神宝を悉く焼失したこと等が、茨城県神社誌に記載されています。
祭神は、その名の通り、国之常立神(くにのとこたちのかみ)、豊雲野神(とよぐもぬのかみ)に始まる天神七代の神々(7代12柱)の12神で、歴史のある神社です。
十二所神社の春季例大祭は、大子町指定文化財となっています。春季例大祭は毎年開催されますが、神輿の神幸は4年に1度となります。境内には大鳥居、百段階段、聖徳太子塔、蒟蒻神社などがあり、茨城百景「大子の史跡」の一部とされています。毎年、3月初めに行われる百段階段のひな祭りは有名です。御朱印は、社務所で拝受できます。
所在地〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子458
連絡先:十二所神社・電話:0295-72-0816
参考大子町 十二所神社春季例大祭 紹介ページ
十二所神社の地図表示
十二所神社 蒟蒻神社:おすすめスポット
蒟蒻神社は、十二所神社の境内社で、奥久慈地方の蒟蒻業界の始祖と云われる中島藤右衛門翁(1745年~1825年)を祀った神社です。
※中島藤右衛門は、常陸国(茨城県)久慈郡諸沢村の農民で、蒟蒻製法の発明者です。久慈郡北部の山地では古くからこんにゃく芋が栽培されていました。 収穫した生芋は、重量もあり、腐敗や凍結しやすかったためその流通には問題がありました。藤右衛門は、安永5(1776)年ごろに生芋を輪切りにし、自然乾燥したあと粉にすることを考案しました。これによって長期保存や軽量化が可能となり、販路が拡大し、水戸藩の特産物となりました。水戸藩は、文化3(1806)年に、藤右衛門に苗字帯刀と麻裃着用を許し、その功を称えたという実話です。
- 所在地〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子
- 参考大子町観光協会 蒟蒻神社 紹介ページ
蒟蒻神社の地図
諏訪神社の鳥居景観・神馬像とVRツアーの説明
小生瀬の諏訪神社の鳥居景観と境内の神馬像の写真とVRツアーの説明です。
諏訪神社の鳥居景観
 大子町小生瀬の諏訪神社入口の鳥居景観です。国道461号の南側に行く丁字路があり、そこに諏訪神社の看板があります。そのまま100m程進むと右側に鳥居が見えます。鳥居の反対側にも2台程度の駐車スペースはありますが、正式には、そのまま緩やかな坂を上って鳥居から約150mのところの右側に「諏訪神社(表参道)」という看板があります。その入り口を進むと広い駐車スペースがあります。
大子町小生瀬の諏訪神社入口の鳥居景観です。国道461号の南側に行く丁字路があり、そこに諏訪神社の看板があります。そのまま100m程進むと右側に鳥居が見えます。鳥居の反対側にも2台程度の駐車スペースはありますが、正式には、そのまま緩やかな坂を上って鳥居から約150mのところの右側に「諏訪神社(表参道)」という看板があります。その入り口を進むと広い駐車スペースがあります。諏訪神社の随伸門前の神馬像の案内
 髄神門前の神馬像の写真です。佐竹氏の紋が入っています。この地は、平安時代以前は、陸奥国でした。大子町や福島県の塙町付近は、佐竹氏と白川結城氏の支配が漸次入れ替わるという激戦の地でした。諏訪神社のすぐ西側は、月居山で、そこにはかつて月居城があり、佐竹氏の奥州攻略の軍役負担と前線基地の役割を果たした要所でした。そのため、戦勝祈願を度々行ったと思われ、当時は実際に生きた馬を奉納していたと考えられます。神馬像の左側の石碑には、「雨を祈るには黒毛の馬を、晴れを祈るには白毛の馬を奉納する」という習わしが記載されています。これは、次の記載の平安時代中期の延期式に記載されている内容です。
髄神門前の神馬像の写真です。佐竹氏の紋が入っています。この地は、平安時代以前は、陸奥国でした。大子町や福島県の塙町付近は、佐竹氏と白川結城氏の支配が漸次入れ替わるという激戦の地でした。諏訪神社のすぐ西側は、月居山で、そこにはかつて月居城があり、佐竹氏の奥州攻略の軍役負担と前線基地の役割を果たした要所でした。そのため、戦勝祈願を度々行ったと思われ、当時は実際に生きた馬を奉納していたと考えられます。神馬像の左側の石碑には、「雨を祈るには黒毛の馬を、晴れを祈るには白毛の馬を奉納する」という習わしが記載されています。これは、次の記載の平安時代中期の延期式に記載されている内容です。
神社と馬の信仰について
小生瀬の諏訪神社の地図
男体神社:大子町頃藤
男体神社は、大子町頃藤にある大同2年(807年)創建の神社です。
祭神は、男体山山頂(標高653m)の奥の院(石祠)に「伊邪那岐命」を主神として祀り、西側の長福山(女体神社:標高496m)の山頂の石祠に「伊邪那美命」を祀り、両方一体として男体神社に祀っています。男体山の山頂と長福山の山頂の直線距離は、約1.2キロメートルでほぼ中間点(標高291m)に位置します。
古くから農業の神、漁業の神として信仰が厚く、農業の神として作物の五穀豊穣や嵐除け祈願、漁業の神としては、大漁祈願、出漁の安全祈願が行なわれました。
当山は、太平洋も眺められ、船の位置航路を測定出来るため、かつて艏掛山(ふねのけやま)とも呼ばれていました。
また、男体神社の裏側には、「白糸の滝」があります。かつて男体神社は、神仏習合で山頂の奥宮(奥の院)は、禅頂殿とも呼ばれ、修験者が白糸の滝で身のけがれを払い、禅頂殿を参籠(さんろう)し、太平洋の朝日を排し祈願したそうです。
※文章は、茨城県神社誌を参照、文中の「参籠」は、一定期間こもって祈願すること。
なお、男体神社や白糸の滝には、登山口の駐車場まで車で行けるため観光でも容易にご覧いただけます。奥宮までは、トレッキングシューズ等登山の装備が必要です。
大子町の男体神社の地図
関戸神社:大子町の古社
関戸神社は、別名、関戸米神社ともいわれる大子町頃藤にある古社です。
御祭神:天津彦根命(あまつひこねのみこと)
社伝によると大同元年(806)の創建で、往古源義家北征に当たり、この地を陸奥国白川郡と常陸国久慈郡の国境と定め、ここに「関戸米神社」を祀り戦勝を祈願したといわれています。 神社名の由来は、平安時代以前は、奥州南西部の白川郡と常陸国久慈郡の境界(焼山関)があったことに由来します。 関戸神社は、「関戸神社(焼山関)」として、大子町の史跡文化遺産となっています。
- (1)「今昔物語集」巻27第45話の記載
- 「陸奥国ヨリ常陸ノ国へ超ル山ヲバ、焼山ノ関トテ極ジク深キ山ヲ通ル也」
陸奥国から常陸国に入るとき、焼山の関所という大変深い山を通りました。)とあります。
※「今昔物語集』(こんじゃくものがたりしゅう)とは、平安時代末期に成立したとされる「むかし、むかし」で始まる説話集です。 - (2)『新編常陸国誌』の記載
- 新編常陸国誌には、「焼山関」を「多岐也麻乃世幾」とよみ、「凡本国久慈郡ヨリ陸奥ノ白河郡ニ入ルベキ道ニアリ。今ノ久慈郡比藤村(古奥州白川郡)ニ関戸明神アリ、コレ其地ナリ」と記されています。
古来、関戸神社は、関戸大明神の有り難い御霊験により、人々の不幸災難の入り込むことを関戸米(せきとめ)て、心の青浄安泰を護持する守護神といわれています。 御祭神の天津彦根命は、農耕商工業の繁栄の基を開き、疫疾厄災を祓い、幸福招来、和合円満の御神徳は厚く尊敬されております。 ※「往古」又は平安時代以前の頃藤は、常陸国ではなく陸奥国でした、鎌倉時代以降、佐竹氏が陸奥国南部に進軍し、白川結城氏と勝ち負けを繰り返し、佐竹義舜の代の永正年間(1504年~1521年)以降、江戸時代末まで常陸国になったという経緯があります。
なお、現在は、関戸神社の宮司が男体山の奥宮を含めた男体神社をはじめとして頃藤地域の神社を統括しています。御朱印は、境内の西側口の社家でいただけます。念のため事前に電話してください。
所在地〒319-3361 茨城県久慈郡大子町頃藤6506
連絡先関戸神社・電話:0295-74-0501
関戸神社の地図
越方神社:大子町の相川鎮守
越方神社は、大子町相川にある朱塗りの太鼓橋と鳥居が目立つ神社です。
御祭神:経津主命 (ふつぬしのみこと)、大巳貴命 (おおなむちのみこと)
茨城県神社誌には、社伝では、大同年間(806年~810年)の創立と伝わり、越方大明神と尊称されていたこと、慶長18年(1613年)に、三輪神社を合併し越方神社になったことが記載されています。麻疹の神としての信仰され、「橋くぐり」という信仰があり、神橋を潜ると病難を免れると云われています。
神社の境内の規模は小さいながらも御神水、朱色の神橋や鳥居、髄神門もあり、地域の鎮守としては立派な神社で大子町おすすめ観光スポットです。社務所はありません。
所在地〒319-3534 茨城県久慈郡大子町相川1101
連絡先越方神社・電話:0295-72-0816
越方神社の太鼓橋・拝殿とVRツアーの案内
以下は、太鼓橋と拝殿の景観写真です。本写真おける越方神社の観光スポットのVRツアーの説明です。上記の鳥居の写真も含めて写真をクリックするとVRシーンが表示されます。上記の「橋くぐり」は、読んだだけでは意味が分かりませんが、実際に現地に行くと納得します。本サイトのVRツアーでも体験できます。
赤い太鼓橋は、相川に架かった橋で渡り終えるとすぐに赤い鳥居の前です。
橋をくぐるという記載だけでは意味不明ですが、鳥居の前の左右に階段があり、下ったところにコンクリートの狭い通路があり通り抜けられるようになっています。VRツアーで説明板を確認できますが、緒方神社入口の説明板には3回くぐることが記載されています。周り方は記載されていません。「3回くぐる」で思い出すのが神社の無病息災の祈願行事の「地の輪くぐり」です。「地の輪くぐり」は、左、右、左まわりで3回ります。なお、橋くぐりは、
越方神社の拝殿前の景観と髄神門の御神像
 越方神社の拝殿前の景観です。VRシーンでは進むと向拝です。戻ると髄神門の前です。この場所のVRシーンを回転させると髄神門の裏側で、髄神門に安置された左右の守護神の石の御神像を見ることができます。拡大するとわかりますがかなり古いものです。神社誌には、天保6年(1835年:江戸時代末期)に随神門が新築されたことが記載されていますが、それ以前、創建の頃から野外にあったことが想像されます。
越方神社の拝殿前の景観です。VRシーンでは進むと向拝です。戻ると髄神門の前です。この場所のVRシーンを回転させると髄神門の裏側で、髄神門に安置された左右の守護神の石の御神像を見ることができます。拡大するとわかりますがかなり古いものです。神社誌には、天保6年(1835年:江戸時代末期)に随神門が新築されたことが記載されていますが、それ以前、創建の頃から野外にあったことが想像されます。
神社等の橋くぐり祈願にとは:越し方神社は、橋くぐりが可能な日本唯一の場所?
緒方神社の地図
大子町の神社説明における参考文献
本ページに記載の内容は、以下の文献等を参考にして記載しています。 なお、写真やVR写真は、茨城VRツアーの現地取材で撮影したものです。
- 茨城県神社誌:発行者・茨城県神社庁:発行日・昭和48年6月20日
- 取材時における神社の由緒説明板の記載内容、及び神社のホームページ
- 市町村の文化財等説明の参照
- 用語等におけるWikipediaの参照